すべては繋がっている?:カプラとプリゴジンが提唱し、現代科学が証明した「システム生命観」のすべて
もし、宇宙全体が巨大な機械ではなく、絶えず変化し、自己創造を続ける「生きたネットワーク」だとしたら? 20世紀の物理学革命の中で生まれたこの問いは、今や空想ではありません。物理学者フリッチョフ・カプラが東洋思想に見出したビジョンと、ノーベル賞学者イリヤ・プリゴジンが解き明かした「自己組織化」の原理。かつては詩的とされたこれらの洞察が、複雑系科学、ネットワーク科学、量子生物学といった最先端の研究によって、驚くべき精度で「真実」であったことが証明されつつあります。この記事では、デカルト以来の古い世界観の崩壊から、すべてが繋がる新しいパラダイムの確立まで、壮大な知的探求のすべてを辿ります。
序論:二つの世界を繋いだ物理学者のビジョンとその実現
1970年代、一人の理論物理学者が、ある夏の午後に体験した鮮烈なビジョンをきっかけに、科学と精神性の世界に橋を架ける壮大な知的探求へと乗り出しました。その物理学者の名はフリッチョフ・カプラ。彼は、絶え間ない創造と破壊の中でエネルギーが踊る「コズミック・ダンス」の幻視を、ヒンドゥー教の神シヴァの舞踊に重ね合わせました。この個人的な体験が、現代物理学の最先端と古代東洋の神秘主義との間に存在する深遠な共鳴を暴き出す世界的ベストセラー『タオ自然学』(The Tao of Physics, Shambhala Publications, 1975)の原点となったのです。
しかし、カプラの探求はそこで終わりませんでした。素粒子の世界の比喩的な類似性だけでは、私たちが直面する環境破壊や社会の分断といった「生命」のシステムが抱える危機を解決することはできない。この認識が、彼を次なる問いへと向かわせます。「生命とは何か?」そして「なぜ宇宙は、無秩序へと向かうはずの物理法則の中で、これほどまでに精緻な生命の秩序を生み出すことができるのか?」
この問いに答えるため、カプラは自身の思索を物理学から生命科学、システム理論へと拡張していきます。その過程で決定的に重要となったのが、ノーベル化学賞受賞者イリヤ・プリゴジンが提唱した「自己組織化」の理論でした。プリゴジンとイザベル・ステンゲルスの共著『混沌からの秩序』(Order Out of Chaos, Bantam Books, 1984)は、熱力学第二法則と生命の秩序の謎を解く鍵を提供しました。
本稿では、この二人の巨人の思想を軸に、一つの壮大なパラダイムシフトの物語を解き明かしていきます。まず、西洋科学を支配した機械論的世界観の崩壊から始め、次に『タオ自然学』が示した量子世界と東洋思想の驚くべきパラレルを探ります。そして、プリゴジンの「散逸構造論」が、いかにして生命の創造性の謎を解く鍵となったかを明らかにし、最終的にカプラが『生命の網』(The Web of Life, Anchor Books, 1996)の中で、それら全ての知見をいかにして「システム生命観」という包括的なフレームワークへと織り上げていったのかを追跡します。
さらに重要なことに、本稿では1990年代以降の科学的発展が、カプラの予見をいかに実証し、発展させたかを詳述します。サンタフェ研究所の複雑系科学、アルバート=ラズロ・バラバシのネットワーク科学、システム生物学、量子生物学、そして身体化認知科学の最新の知見を通じて、カプラの統合的ビジョンが現代科学の主流となっていく過程を明らかにします。これは、宇宙のダンスから生命の網へ、そして混沌からの秩序の創発へと至る、新しい科学的世界観の誕生と成熟の物語です。
第1部:機械仕掛けの宇宙の終焉
デカルトとニュートンの遺産:機械論的世界観
何世紀にもわたり西洋科学と文化を支配してきたのは、16世紀から17世紀にかけて確立された「機械論的世界観」でした。ルネ・デカルトとアイザック・ニュートンによって体系化されたこのパラダイムは、宇宙を巨大な機械として捉えます。その核心には、以下のような信念がありました。
還元主義:宇宙は、原子のような根本的で堅固な構成要素に分解でき、全体は部分の総和に過ぎない。複雑な現象も、その部分を研究することで完全に理解できる。この思想は、デカルトの『方法序説』(1637年)に明確に表現されています。
心身二元論:デカルトは精神(思惟)と物質(延長)を明確に分離しました。これにより、自然は魂のない客体となり、人間はそれを外から観察し、支配し、利用する特権的な存在と見なされるようになりました。この二元論は、西洋文明における自然からの疎外の哲学的基盤となりました。
決定論的宇宙:ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』(1687年)に従い、すべての物体の運動は正確に予測可能であるとされました。宇宙は、神が最初に設定した法則に従って動く、巨大な時計仕掛けのようなものだったのです。ラプラスの悪魔という思考実験は、この決定論的世界観の極致を示しています。
この世界観は、科学技術の驚異的な発展を促しました。産業革命、医学の進歩、宇宙開発など、人類の偉大な成果の多くはこのパラダイムの産物です。しかし同時に、自然からの疎外、精神と物質の分離、そして現実に対する断片的な理解をもたらし、環境破壊、精神的空虚、社会の分断といった現代の危機の根源ともなりました。
物理学の危機:二つの革命がもたらしたもの
しかし、20世紀初頭、アルベルト・アインシュタインの相対性理論と、量子力学の発見という二つの革命が、この堅固な機械論パラダイムを根底から揺るがしました。
相対性理論の衝撃:1905年の特殊相対性理論と1915年の一般相対性理論は、空間と時間が絶対的なものではなく、観測者に対して相対的であり、重力によって歪むことを示しました。E=mc²という方程式は、物質とエネルギーの等価性を示し、「堅固な物質」という概念を根本から覆しました。
量子力学の逆説:マックス・プランク、ニールス・ボーア、ヴェルナー・ハイゼンベルク、エルヴィン・シュレーディンガーらが発展させた量子力学は、原子以下のミクロの世界が、常識とは全く異なる奇妙な法則に支配されていることを明らかにしました。ニュートンの描いた堅固で予測可能な粒子は、確率の波、パラドックス、そして不可分な繋がりの世界へと姿を変えたのです。
ハイゼンベルクの不確定性原理(1927年)は、粒子の位置と運動量を同時に正確に知ることが原理的に不可能であることを示しました。これは単なる測定の技術的限界ではなく、自然の根本的な性質でした。ニールス・ボーアは「量子世界を理解したと思う人は、それを理解していない証拠である」と述べ、この新しい現実の逆説的な性質を強調しました。
この「物理学の危機」は、もはや古い言葉では現実を記述できないことを科学者たちに突きつけ、世界を理解するための全く新しい思考法を必然的に要求しました。ボーアは相補性原理を提唱し、粒子性と波動性のような相反する性質が、現実の相補的な側面であることを示しました。これは、西洋の二元論的思考の限界を露呈させる革命的な洞察でした。
第2部:古代の叡智との共鳴:『タオ自然学』の深層
この新しい物理学が描き出す世界像の中に、古代東洋の神秘家たちが直観的に捉えた世界観との驚くべき類似性を見出したのが、フリッチョフ・カプラでした。『タオ自然学』の核心は、その具体的なパラレルの探求にあります。
統一性と相互接続性:量子もつれが示す不可分の世界
量子論が明らかにしたのは、素粒子が孤立した「モノ」ではなく、分離不可能な宇宙的ウェブにおける「相互関係」の束であるという事実です。1935年のアインシュタイン=ポドルスキー=ローゼン(EPR)パラドックスは、量子もつれという現象を理論的に予言し、1982年のアラン・アスペの実験によって実証されました。この実験は、遠く離れた粒子が瞬時に相互作用することを証明し、局所性という古典的概念を完全に覆しました。
この洞察は、東洋思想の核心と深く共鳴します:
ヒンドゥー教のブラフマン:『ウパニシャッド』における「タット・トヴァム・アシ」(汝はそれなり)という教えは、万物が単一の究極的実在の現れであるとする、非分離・不可分の統一体としての世界観です。リグ・ヴェーダの「インドラの網」の比喩は、宇宙のあらゆる点に全体が反映される相互浸透的な現実を描写しており、ホログラフィック原理を予見していました。
仏教の縁起思想:龍樹の『中論』で体系化された縁起(プラティーティヤ・サムトパーダ)の思想は、何一つとしてそれ自体で独立して存在することはなく、すべてが他のすべてとの関係性においてのみ存在するという考え方です。華厳経の「一即一切、一切即一」という表現は、量子もつれが示す非局所的相関と驚くほど類似しています。
道教の相互依存性:老子の『道徳経』における「有と無は相生じ、難と易は相成り、長と短は相形る」という記述は、対立するものが実は相互依存的であることを示しており、量子力学における波動-粒子の相補性と深く共鳴します。
動的な宇宙とコズミック・ダンス:エネルギーの永遠の舞踏
素粒子物理学の実験、特にバブルチェンバーやウィルソン霧箱での観測は、ミクロの世界が静的な存在ではなく、粒子が常に生成と消滅を繰り返すエネルギーのダイナミックな舞踏であることを示しています。真空でさえも、仮想粒子の絶え間ない生成と消滅で満ちた「量子真空」であることが明らかになりました。
カプラはこの光景に、宇宙を維持する創造と破壊の永遠のサイクルを象徴するヒンドゥー教のシヴァ神の宇宙的な舞踏、ナタラージャという力強いメタファーを見出しました。シヴァの舞踏は、リズミカルな動きを通じて宇宙を創造し、維持し、破壊する永遠のプロセスを表現しています。これは、量子場理論が描く、エネルギーの絶え間ない変換と粒子の生成・消滅のプロセスと見事に対応しています。
興味深いことに、CERN(欧州原子核研究機構)には、インド政府から寄贈されたナタラージャの像が設置されています。これは、現代物理学と古代の叡智の対話を象徴する powerful な証となっています。
現実の逆説的な性質:論理を超えた真実
量子力学は、常識や古典論理に反するパラドックスに満ちています:
粒子と波動の二重性:1801年のトマス・ヤングの二重スリット実験は、光が波動性を持つことを示しましたが、1905年のアインシュタインの光電効果の説明は光の粒子性を証明しました。電子は、観測方法によって粒子のようにも波動のようにも振る舞います。これは「AかBか」という二者択一の論理の限界を示しています。
オッペンハイマーのパラドックス:ロバート・オッペンハイマーは「電子は静止しているかと問うなら、『否』。では運動しているかと問うなら、これも『否』である」と述べました。これは、『イーシャ・ウパニシャッド』の「それは動き、しかも動かない。それは遠く、しかも近い」という逆説的な表現と見事に呼応します。
シュレーディンガーの猫:1935年に提案されたこの思考実験は、量子的な重ね合わせ状態という概念を巨視的世界に拡張したもので、生と死が同時に存在するという逆説を提示します。これは禅の公案「生死一如」と深く共鳴します。
このような逆説は、西洋的な「AかBか」という二者択一の論理(排中律)とは対照的に、道教の陰陽思想や禅の公案のように、理性的思考を超越するためにパラドックスを用いる東洋の思考法と親和性があります。禅僧道元の「身心脱落」や、龍樹の「四句否定」(テトラレンマ)は、二元論的思考の限界を超える方法論を提供しています。
観測者の役割:意識と現実の不可分性
量子物理学における「観測者効果」は、観測するという行為そのものが、観測対象の現実に影響を与えることを示し、主観と客観の境界線を曖昧にします。これは、純粋に客観的で分離した科学者という古典的な理想を覆すものです。
ジョン・ホイーラーの「参加型宇宙」という概念は、観測者が単なる傍観者ではなく、現実の創造に参加する存在であることを示唆します。彼の「遅延選択実験」は、現在の観測が過去の現実を決定することを示し、時間と因果関係の古典的理解に挑戦しました。
この発見は、意識が現実の受動的な観察者ではなく、それを構成する能動的な参加者であると考える神秘主義の伝統と共鳴します。ヴェーダーンタ哲学における「見る者と見られるものの統一」、仏教唯識派の「三界唯心」、道教の「観察者と観察対象の相互浸透」などの教えは、この洞察を何世紀も前から示していました。
科学と神秘主義:相補的な認識の道
カプラは、科学と神秘主義が同一であると主張したのではありません。むしろ、それらは現実に対する相補的なアプローチであると説きます。科学が理性的・分析的な精神を用いるのに対し、神秘主義は直観的・全体的な精神を用います。「科学に神秘思想はいらないし、神秘思想に科学はいらない。だが、人間には両方とも必要なのだ」という彼の言葉が、この思想の核心を突いています。
この相補性の認識は、現代の認知科学における「二重過程理論」(システム1とシステム2)や、脳科学における左脳・右脳の機能分化の理解とも合致します。統合的な認識には、分析的思考と直観的洞察の両方が必要であることが、科学的にも実証されつつあります。
第3部:混沌からの秩序の創発:イリヤ・プリゴジンの革命的科学
『タオ自然学』が提示したパラダイムは強力でしたが、それはあくまで物理学の領域における比喩的な類似性でした。生命の世界に目を転じると、より根源的な謎が残されていました。熱力学第二法則によれば、宇宙全体のエントロピー(無秩序さ)は増大し続けるはずなのに、なぜ地球上では生命のような高度に秩序化された複雑なシステムが生まれ、進化し続けることができるのでしょうか?
この問いに決定的な答えを与えたのが、ベルギーの物理化学者イリヤ・プリゴジンでした。彼のノーベル賞受賞(1977年)につながる研究は、カプラが後に構築する生命の科学に、不可欠な物理的基盤を提供することになります。
「散逸構造」と自己組織化の発見
プリゴジンは、生命のようなシステムが、外部とエネルギーや物質を交換し続ける「開放系」であり、かつ熱力学的な「平衡から遠く離れた状態」にあることに着目しました。彼の主著『存在から生成へ』(From Being to Becoming, 1980)において、彼は時間の本質的な役割と不可逆性の創造的な性質を明らかにしました。
プリゴジンの理論の核心は以下の発見にあります:
ゆらぎと分岐:平衡から遠い系では、微小な「ゆらぎ」が系の運命を決定する可能性があります。ある臨界点(分岐点)において、系は複数の可能な状態のうちの一つを「選択」し、全く新しい秩序状態へと移行します。これは決定論と偶然性が共存する新しい世界観を提示しました。
散逸構造の概念:プリゴジンは、エネルギーや物質を外部と交換し、散逸させ続けることによってのみ維持される動的で秩序だった構造を「散逸構造(dissipative structure)」と名付けました。これは静的な平衡構造とは根本的に異なる、動的で生きた構造です。
自己組織化のメカニズム:外部からの指令や設計図なしに、システムが自らの内部的なダイナミクスによって、無秩序から秩序を自発的に形成する能力を「自己組織化」と呼びました。これは生命の本質的な特性であることが明らかになりました。
散逸構造の具体例と実験的検証
プリゴジンの理論は、多くの自然現象で実証されました:
ベナール対流:鍋の底を加熱すると、ある臨界温度差で突然、規則的な六角形の対流パターン(ベナールセル)が現れます。これは熱エネルギーの散逸を通じて秩序が自発的に生まれる典型例です。
ベロウソフ・ジャボチンスキー反応:この化学反応では、溶液の色が規則的に振動し、美しい螺旋パターンを形成します。これは化学系における時空間的な自己組織化の実例です。
生物学的リズム:心臓の拍動、概日リズム、神経細胞の同期発火など、生命現象の多くが散逸構造として理解できることが明らかになりました。
生態系と進化:生態系全体が巨大な散逸構造であり、太陽エネルギーの流れを通じて複雑な食物網と多様性を維持していることが示されました。
プリゴジンの理論は、生命が決して物理法則の「例外」なのではなく、むしろ「平衡から遠く離れた」特殊な条件下で物理法則が必然的にもたらす帰結であることを示しました。創造性、つまり新しい形態の生成は、生命システムの根源的な特性だったのです。
時間の矢と不可逆性の創造的役割
プリゴジンの最も革命的な貢献の一つは、時間の本質に関する新しい理解でした。古典物理学では時間は可逆的でしたが、プリゴジンは不可逆性こそが創造性の源泉であることを示しました。『確実性の終焉』(The End of Certainty, 1997)において、彼は時間が単なるパラメータではなく、新しさを生み出す演算子であることを論証しました。
この時間観は、アンリ・ベルクソンの「創造的進化」やアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドのプロセス哲学と深く共鳴し、東洋思想における「無常」の概念とも呼応します。変化と流転こそが現実の本質であり、永遠不変なものは幻想であるという洞察が、科学的に基礎づけられたのです。
第4部:生命の網の科学:『Web of Life』とシステム生命観の確立
『タオ自然学』から約20年後の1996年、カプラは『生命の網』において、プリゴジンらの科学的発見を統合し、機械論的世界観に代わるべき後継パラダイムとして「システム生命観」を提唱しました。ここでの焦点は、モノから関係性へ、構造からプロセスへ、そして構成要素からパターンへと劇的に移行します。
生命システムの三位一体モデル
カプラは、生命システムを完全に理解するためには、以下の三つの側面を統合する必要があると考えました。この三位一体のフレームワークこそ、彼の思想の集大成です:
1. 組織のパターン(Pattern of Organization):オートポイエーシス
チリの生物学者ウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラによって1972年に提唱された「オートポイエーシス」は、生命を定義する上で極めて重要な概念です。彼らの著書『オートポイエーシス:生命システムの組織』において、生命とは「オートポイエーシス・システム」、つまり自らを構成する要素を絶えず生産し続けるプロセスのネットワークであり、自らと環境とを区別する境界を自律的に創り出すシステムであると定義されます。
機械が「アロポイエティック(他者によって作られる)」のに対し、生命は「オートポイエーティック(自己創出的)」であり、その第一の機能は自分自身を生産し維持することにあります。細胞は、その代謝ネットワークを通じて自らの構成要素(タンパク質、脂質、核酸など)を絶えず生産し、同時にそれらの構成要素が代謝ネットワークそのものを形成するという、循環的な因果関係を持っています。
2. 構造(Structure):散逸構造
これは、「組織のパターンを物理的に具現化するもの」です。カプラは、生命システムの物理的な構造こそが、プリゴジンの言う「散逸構造」であると明確に位置づけました。生命体は、環境から物質とエネルギーを取り込み、代謝(散逸)し続けることで、そのオートポイエティックなパターンを維持する、具体的な物理的実体なのです。
例えば、人体は約7年で全ての原子が入れ替わると言われていますが、その「パターン」は維持されます。これは、生命が物質の特定の配置ではなく、物質とエネルギーの流れのパターンであることを示しています。川の渦巻きが水分子の特定の集合ではなく、水の流れのパターンであるのと同様です。
3. 生命のプロセス(Life Process):認知
これは、「組織のパターンを特定の構造の中に絶えず具現化し続ける活動」です。カプラは、マトゥラーナとヴァレラの革命的な洞察を取り入れ、このプロセスを「認知」と同一視しました。彼らの『認知の生物学』において、認知とは脳の中だけで起こるものではなく、生命のプロセスそのものであることが示されています。
バクテリアが栄養源に向かって泳ぐとき、植物が光に向かって成長するとき、免疫システムが抗原を認識するとき、これらすべてが認知プロセスです。環境と相互作用し、それに応じて自らの振る舞いを変化させる生命システムはすべて、認知プロセスに従事しているのです。この視点は、デカルト的な心身二元論をその根源から解消します。
この三位一体のモデルにおいて、プリゴジンの散逸構造は、生命という抽象的な「パターン」と、生きるという具体的な「プロセス」とを結びつける、不可欠な「構造」として位置づけられています。これにより、カプラのシステム生命観は、単なる哲学的示唆を超え、物理的な現実に根ざした強力な科学理論となったのです。
ガイア理論との統合
カプラは、ジェームズ・ラブロックとリン・マーギュリスが提唱したガイア理論を、システム生命観の重要な要素として組み込みました。地球全体が一つの自己調節的な生命システムであるという考えは、オートポイエーシスの概念を惑星規模に拡張したものと理解できます。
大気中の酸素濃度が21%に保たれていること、海洋の塩分濃度が3.5%前後で安定していること、地球の平均気温が生命に適した範囲に維持されていることなど、これらすべてが地球という巨大な散逸構造の自己組織化プロセスの結果として理解できます。
第5部:1990年代以降の科学的検証と発展
カプラの予見的なビジョンは、1990年代以降の科学の急速な発展によって、驚くべき検証と拡張を経験しました。複雑系科学、ネットワーク科学、システム生物学、量子生物学などの新しい分野が、彼の統合的世界観に強力な実証的基盤を提供しています。
サンタフェ研究所と複雑系科学の確立
1984年に設立されたサンタフェ研究所は、物理学者マレー・ゲルマン、経済学者ケネス・アロー、コンピュータ科学者ジョン・ホランドらによって、複雑系を研究する学際的な研究機関として創設されました。この研究所は、カプラが提唱した分野横断的アプローチを制度的に実現したものと言えます。
スチュアート・カウフマンと自己組織化の数学
スチュアート・カウフマンは『宇宙の始まりと生命の意味』(At Home in the Universe, 1995)において、生命の出現が偶然の産物ではなく、自然の秩序の必然的な実現であることを数学的に示しました。彼の理論の主要な貢献は:
NKモデル:カウフマンが開発したNKモデルは、N個の要素がそれぞれK個の他の要素と相互作用するシステムの進化を記述します。このモデルは、K=2付近で「カオスの縁」と呼ばれる領域が現れ、そこで最も効率的な進化と適応が起こることを示しました。これは生命システムが秩序と無秩序の境界で機能することを数学的に証明したものです。
自己触媒セット理論:化学反応ネットワークにおいて、分子の多様性がある臨界値を超えると、自己触媒的な反応ループが自発的に形成されることを示しました。これは生命の起源に関する新しい理論的枠組みを提供し、「RNAワールド」仮説を補完するものとなりました。
ブーリアンネットワーク:遺伝子制御ネットワークのモデルとして、ランダムブーリアンネットワークを研究し、適切なパラメータ設定で自発的に安定したアトラクターが形成されることを示しました。これは細胞分化のメカニズムを説明する有力なモデルとなっています。
ジョン・ホランドと複雑適応系
ジョン・ホランドは『Hidden Order』(1995)と『Emergence』(1998)において、複雑適応系(Complex Adaptive Systems, CAS)の理論を確立しました。彼の主要な貢献は:
遺伝的アルゴリズム:生物進化の原理を計算機科学に応用し、最適化問題を解く強力な手法を開発しました。これは現在、工学、経済学、人工知能など幅広い分野で応用されています。
エージェントベースモデリング:個々のエージェントの相互作用から創発する集団的行動をシミュレートする手法を開発し、経済市場、生態系、社会システムの理解に革命をもたらしました。
創発の階層理論:単純なルールに従う要素の相互作用から、予測不可能な高次の秩序が創発するメカニズムを理論化しました。
パー・バクと自己組織化臨界現象
デンマークの物理学者パー・バクは、1987年の画期的な論文で自己組織化臨界現象(Self-Organized Criticality, SOC)の概念を提唱しました。彼の著書『自然のしくみ』(How Nature Works, 1996)は、この理論を一般向けに解説したものです:
サンドパイルモデル:砂山に砂粒を一つずつ落としていくと、システムは自然に臨界状態に達し、雪崩の規模がべき乗則に従う分布を示すことを発見しました。小さな雪崩は頻繁に起こり、大きな雪崩は稀にしか起こりません。
普遍性:この1/fノイズやべき乗則は、地震の規模分布(グーテンベルク・リヒター則)、森林火災の規模、生物の大量絶滅、株式市場の変動など、自然界の至る所で観察されることを示しました。
臨界性への自己組織化:システムが外部からの調整なしに、自然に臨界状態へと進化することを示し、なぜ自然界にフラクタル構造やべき乗則が普遍的に見られるかを説明しました。
2021年のScientific Reportsに発表された研究では、オリジナルのBak-Tang-Wiesenfeldモデルの詳細な解析により、1/xべき乗則がより正確にシステムの挙動を記述することが示されました。
ネットワーク科学革命:バラバシとスケールフリーネットワーク
1999年、アルバート=ラズロ・バラバシとレカ・アルバートはScience誌に「ランダムネットワークにおけるスケーリングの創発」という論文を発表し、ネットワーク科学に革命をもたらしました。
スケールフリーネットワークの発見
バラバシらは、インターネット、ワールドワイドウェブ、代謝ネットワーク、タンパク質相互作用ネットワークなど、現実世界の多くのネットワークが「スケールフリー」特性を持つことを発見しました:
優先的結合:新しいノードは、既に多くの接続を持つノード(ハブ)により高い確率で接続する傾向があります。「富める者はますます富む」というマタイ効果が働きます。
べき乗則次数分布:ノードの接続数(次数)の分布がべき乗則P(k)~k^(-γ)に従い、少数のハブと多数の低次数ノードが共存します。
ロバスト性と脆弱性:スケールフリーネットワークは、ランダムな故障に対しては極めて頑健ですが、ハブを狙った攻撃には脆弱です。これはインターネットのセキュリティや、疾患の治療戦略に重要な示唆を与えます。
スモールワールド現象
1998年、ダンカン・ワッツとスティーブン・ストロガッツは「スモールワールドネットワーク」の数学的モデルを提案しました。彼らは、高いクラスタリング係数と短い平均経路長を併せ持つネットワークが、自然界や社会に普遍的に存在することを示しました。
「六次の隔たり」という概念が数学的に基礎づけられ、脳の神経ネットワーク、社会ネットワーク、電力網などがスモールワールド特性を持つことが実証されました。
システム生物学の確立と発展
2000年代に入り、システム生物学は独立した学問分野として確立されました。この分野は、カプラのシステム思考を分子生物学に直接適用したものと言えます。
北野宏明とシステム生物学研究機構
ソニーコンピュータサイエンス研究所の北野宏明は、2000年にシステム生物学の概念を提唱し、2002年のScience論文「システム生物学:簡潔な概観」で、この分野の基本原理を確立しました:
ロバストネス:生物システムの最も重要な特性の一つは、環境の変動や内部のノイズに対するロバスト性です。北野は、このロバスト性がフィードバック制御、冗長性、モジュラリティ、適応性の組み合わせによって達成されることを示しました。
システムレベルの理解:個々の分子の機能だけでなく、それらの相互作用ネットワーク全体の動的振る舞いを理解することの重要性を強調しました。
SBML標準:Systems Biology Markup Languageを開発し、生物学的モデルの標準的な記述方法を確立しました。これにより、世界中の研究者がモデルを共有し、検証することが可能になりました。
デニス・ブレイとタンパク質の計算能力
ケンブリッジ大学のデニス・ブレイは、1995年のNature論文「生細胞における計算要素としてのタンパク質分子」で、タンパク質ネットワークが生物学的コンピュータとして機能することを示しました:
アロステリック相互作用:タンパク質の立体構造変化が、複雑な情報処理を可能にすることを実証しました。
シグナル増幅:キナーゼカスケードなどの仕組みにより、微弱なシグナルが増幅されるメカニズムを解明しました。
分子記憶:リン酸化状態の双安定性により、分子レベルでの記憶保存が可能であることを示しました。
ウリ・アロンとネットワークモチーフ
ワイツマン科学研究所のウリ・アロンは、2002年から一連の研究で「ネットワークモチーフ」の概念を確立しました:
フィードフォワードループ(FFL):転写制御ネットワークに頻繁に現れる3ノードのモチーフで、ノイズフィルタリングや応答の遅延などの機能を持ちます。
シングルインプットモジュール(SIM):一つのマスター制御因子が複数の標的遺伝子を制御する構造で、時間的な発現プログラムを生成します。
密集重複レギュロン(DOR):複数の転写因子が複数の標的遺伝子を共同制御する構造で、組み合わせ論的な制御を可能にします。
これらのモチーフは、大腸菌から酵母、線虫、ヒトまで、進化的に保存されていることが示され、生命の設計原理の普遍性を示唆しています。
エピジェネティクスと自己組織化
2010年代以降、エピジェネティクス研究の急速な発展により、遺伝子発現制御における自己組織化の重要性が明らかになりました。
エピゲノムの自己組織化
2021年のnpj Systems Biology and Applicationsに発表された研究では、エピジェネティック修飾のパターンが自己組織化的に形成されることが示されました:
クロマチン構造の動的制御:ヒストン修飾とDNAメチル化の相互作用により、クロマチンの開閉状態が自己組織化的に制御されることが実証されました。
相分離による核内構造形成:転写ファクトリーやヘテロクロマチンドメインなどの核内構造が、液-液相分離により自発的に形成されることが発見されました。
トランスジェネレーショナルエピジェネティクス:環境ストレスに対する適応的なエピジェネティック変化が、数世代にわたって継承されることが実証され、ラマルク的進化の分子メカニズムが明らかになりました。
量子生物学の確立
2000年代後半から、量子力学的効果が生物システムで重要な役割を果たすことが次々と発見され、量子生物学という新しい分野が確立されました。
光合成における量子コヒーレンス
2007年、カリフォルニア大学バークレー校のグレゴリー・エンゲルらは、光合成細菌の光捕集複合体において、量子コヒーレンスが室温で数百フェムト秒持続することを発見しました:
量子ウォーク:励起エネルギーが量子的な重ね合わせ状態で複数の経路を同時に探索し、最も効率的な経路を「発見」することが示されました。
ノイズ支援輸送:適度な環境ノイズが、量子コヒーレンスとデコヒーレンスのバランスを最適化し、エネルギー輸送効率を向上させることが発見されました。
進化的最適化:光合成システムの量子効率が、数十億年の進化を通じて最適化されていることが示唆されました。
鳥の磁気感覚と量子もつれ
2021年、オックスフォード大学とオルデンブルク大学の共同研究により、渡り鳥の磁気感覚に量子もつれが関与することが実証されました:
クリプトクロムの量子特性:鳥の網膜に存在するクリプトクロム4タンパク質が、磁場に敏感な量子力学的性質を示すことが確認されました。
ラジカル対機構:光励起により生成されたラジカル対が、数マイクロ秒間量子もつれ状態を維持し、地磁気の方向を感知することが示されました。
量子コンパス:この量子センサーは、わずか50ナノテスラの磁場変化を検出できることが実証されました。
酵素反応における量子トンネル効果
多くの酵素反応において、量子トンネル効果が反応速度を劇的に向上させることが発見されました:
水素移動反応:アルコール脱水素酵素などにおいて、水素原子がエネルギー障壁を量子的にトンネルすることで、古典的予測より10^6倍速い反応が実現されています。
酵素の動的構造:酵素の構造揺らぎが、トンネル確率を最適化するように進化していることが示唆されています。
ネットワーク医学の実践的応用
バラバシらのネットワーク理論は、医学に革命的な変化をもたらしています。
疾患ネットワークと疾患モジュール
2007年、バラバシらはPNASに「ヒト疾患ネットワーク」を発表し、疾患間の分子的関連を網羅的にマッピングしました:
疾患モジュール:疾患は単一遺伝子の異常ではなく、相互作用するタンパク質群(疾患モジュール)の機能不全として理解されるべきことが示されました。
併存症の予測:ネットワーク上で近接する疾患は高い併存率を示すことが実証され、患者の将来の疾患リスクを予測することが可能になりました。
薬剤再配置:既存薬の新しい適応症を、ネットワーク近接度に基づいて予測する手法が開発され、実際に臨床応用されています。
パーソナライズド医療への応用
システム医学的アプローチにより、個人の分子ネットワークプロファイルに基づく精密医療が実現しつつあります:
ネットワークバイオマーカー:単一分子ではなく、分子ネットワークのパターンを疾患のバイオマーカーとして使用することで、診断精度が大幅に向上しました。
多標的治療戦略:がんなどの複雑な疾患に対して、ネットワークの複数のノードを同時に標的とする治療戦略が開発されています。
動的ネットワークバイオマーカー:疾患の臨界転移を予測する動的ネットワークバイオマーカーの概念が、中国科学院の陳洛南らによって提唱され、早期診断に応用されています。
合成生物学における自己組織化の応用
2000年代以降、合成生物学は自己組織化原理を積極的に活用して、新しい生物システムを設計しています。
人工遺伝子回路
MITのティモシー・ルーらは、自己組織化する遺伝子回路を設計し、複雑な計算や制御を実現しています:
トグルスイッチ:双安定性を示す遺伝子回路を構築し、細胞メモリーを実現しました。
リプレッシレーター:3つの遺伝子が相互に抑制し合う回路により、安定した振動を生成することに成功しました。
論理ゲート:AND、OR、NOT などの論理演算を行う生物学的回路を構築し、細胞内でのプログラマブルな情報処理を実現しました。
パターン形成の人工的制御
チューリングパターンの原理を応用して、人工的な空間パターンを生成する研究が進んでいます:
合成モルフォゲン勾配:人工的なモルフォゲン産生・分解系を構築し、制御可能な濃度勾配を形成することに成功しました。
人工発生プログラム:胚発生を模倣した人工的な細胞分化プログラムを構築し、複雑な多細胞構造の自己組織化を実現しています。
身体化認知とエナクティブアプローチの発展
ヴァレラらが提唱した身体化認知の概念は、認知科学、ロボティクス、人工知能の分野で大きな発展を遂げています。
4E認知の確立
2010年代以降、認知科学において「4E認知」(Embodied, Embedded, Enacted, Extended)のパラダイムが確立されました:
身体化(Embodied):認知は脳だけでなく、身体全体の感覚運動システムに依存することが実証されました。
埋め込み(Embedded):認知は環境との相互作用の中で生じることが示されました。
エナクション(Enacted):認知は世界を受動的に表象するのではなく、能動的に構成することが明らかになりました。
拡張(Extended):スマートフォンなどの道具が認知システムの一部として機能することが示されました。
神経現象学の発展
ヴァレラが提唱した神経現象学は、意識研究において重要な方法論となっています:
一人称と三人称の統合:瞑想実践者の主観的体験と脳活動の同時測定により、意識状態の神経相関が解明されています。
デフォルトモードネットワーク:安静時の脳活動ネットワークが自己意識と密接に関連することが発見されました。
グローバルワークスペース理論:意識が脳全体の情報統合から創発することを示す実証的証拠が蓄積されています。
身体化AIとロボティクス
身体化認知の原理は、新しいタイプの人工知能システムの開発につながっています:
発達ロボティクス:人間の乳幼児の発達過程を模倣することで、自律的に学習するロボットシステムが開発されています。
ソフトロボティクス:柔軟な身体を持つロボットが、環境との相互作用を通じて適応的な行動を生成することが実証されています。
形態学的計算:身体の物理的特性自体が計算資源として機能することが示され、効率的な制御システムの設計に応用されています。
第6部:新たなパラダイムの倫理的・実践的帰結
カプラの科学的枠組みは、単なる理論に留まらず、私たちが世界とどう関わるべきかという倫理的、実践的な指針を与えてくれます。そして、現代の環境危機、パンデミック、社会的分断といった問題に対する具体的な解決策を提供しています。
ディープエコロジー:システム生命観の倫理
カプラの思想は、ノルウェーの哲学者アルネ・ネスが1973年に提唱した「ディープエコロジー」という哲学に、深遠な科学的基盤を提供します。
人間中心主義から生命中心主義へ
機械論的世界観が人間を自然の頂点に置くのに対し、システム生命観は、人間が生命の複雑な網の一本の糸に過ぎないことを示します。この認識は、以下の倫理的帰結をもたらします:
内在的価値:すべての生命が人間にとっての有用性とは無関係に、それ自体で存在する権利(内在的価値)を持つと主張します。生命が自己創出的なネットワークであるならば、そのネットワークのすべての結節点は、全体の完全性にとって不可欠なのです。
生物多様性の重要性:ネットワーク科学は、多様性がシステムのレジリエンスに不可欠であることを数学的に証明しています。生物多様性の喪失は、地球生命システム全体の脆弱化を意味します。
自己実現の拡大:ディープエコロジーは、個人的な「自己(self)」を生命圏全体と一体化する「大いなる自己(Self)」へと拡大することを究極の目標とします。これは、エゴを溶解させて宇宙的全体と合一しようとする神秘主義の目標と軌を一つにします。
システミックな問題には、システミックな解決策を
カプラは、私たちが直面する地球規模の危機(気候変動、経済格差、パンデミックなど)が、すべて相互に関連していると強調します。これらは個別に解決できないシステミックな問題なのです。
気候変動への統合的アプローチ
気候変動は単なる二酸化炭素の問題ではなく、エネルギーシステム、経済システム、社会システム、生態系の複雑な相互作用の結果です:
炭素循環の理解:地球システム科学は、大気、海洋、陸域、生物圏の間の炭素フラックスを統合的にモデル化し、気候感度の予測精度を向上させています。
ティッピングポイント:北極の氷床融解、アマゾン熱帯雨林の乾燥化、永久凍土の融解など、複数のティッピングポイントが相互作用し、カスケード的な変化を引き起こす可能性が指摘されています。
社会-生態システム:エリノア・オストロムらの研究により、コモンズの持続可能な管理には、社会システムと生態システムの結合ダイナミクスを理解することが不可欠であることが示されました。
パンデミックとワンヘルス
COVID-19パンデミックは、人間、動物、環境の健康が不可分であることを劇的に示しました:
ワンヘルスアプローチ:WHO、FAO、OIEが推進するワンヘルスは、人獣共通感染症の予防と制御に統合的アプローチを採用しています。
エコヘルス:生態系の健康と人間の健康の相互依存性を認識し、環境破壊が新興感染症のリスクを高めることが実証されています。
レジリエンス構築:パンデミックに対するレジリエンスは、医療システムだけでなく、社会的ネットワーク、経済システム、ガバナンス構造の統合的強化を必要とします。
実践的応用:理論から行動へ
カプラのシステム思考は、様々な分野で具体的な実践に転換されています:
再生農業と食料システム
土壌マイクロバイオーム:土壌微生物の複雑なネットワークが、植物の健康と炭素隔離に重要な役割を果たすことが解明され、再生農業の科学的基盤となっています。
アグロエコロジー:生態学的原理を農業に応用し、生物多様性、土壌健康、水循環を統合的に管理する手法が開発されています。
食料システムの変革:ローカルフードシステムの構築、食品廃棄物の削減、植物ベースの食事への移行など、システミックなアプローチが推進されています。
循環経済とゼロウェイスト
産業エコロジー:産業システムを生態系のアナロジーで理解し、廃棄物を資源として活用する循環型システムの設計が進んでいます。
クレードル・トゥ・クレードル:製品設計の段階から、材料の完全な循環を考慮したデザイン手法が確立されています。
都市メタボリズム:都市を一つの生命体として捉え、物質とエネルギーのフローを最適化する研究が進展しています。
教育システムの変革
ホリスティック教育:知識の断片的な伝達ではなく、全人的な発達を促す教育アプローチが開発されています。
システム思考教育:MITのピーター・センゲらによる「学習する組織」の概念は、組織学習にシステム思考を導入しています。
生態リテラシー:カプラ自身が設立したCenter for Ecoliteracyは、子供たちに生態系の原理を体験的に学ばせる教育プログラムを開発しています。
この二つの世界観の根本的な違い
機械論的世界観とシステム生命観の対比を、現代科学の知見を含めて整理すると:
| 特徴 | 機械論的世界観 | システム/エコロジー的世界観 |
| 基本メタファー | 世界は機械(時計仕掛け) | 世界はネットワーク/ウェブ(生きたシステム) |
| 現実観 | 分離した部分(原子)の集合 | 不可分で相互接続的な全体(場とプロセス) |
| 科学の焦点 | 還元主義(部分の研究) | 全体論(関係性とパターンの研究)とマルチスケール統合 |
| 核心原理 | 構造、実体、局所的因果関係 | プロセス、パターン、関係性、非局所的相関 |
| 生命観 | 複雑な機械(アロポイエーティック) | 自己創出的なネットワーク(オートポイエーティック) |
| 物理的構造 | 安定した平衡構造 | 平衡から遠い散逸構造、動的安定性 |
| 心(認知)の捉え方 | 脳に宿り、物質と分離した計算装置 | 生命のプロセスそのもの、身体化・埋め込み・拡張された認知 |
| 倫理的立場 | 人間中心主義(アントロポセントリズム) | 生命中心主義(エコセントリズム)、地球中心主義 |
| 問題解決法 | 線形的、断片的な解決策 | システミック、全体的、適応的な解決策 |
| 時間の捉え方 | 可逆的、パラメータ | 不可逆的、創造的、歴史性を持つ |
| 秩序の源泉 | 外部からの設計・制御 | 自己組織化、創発、内在的創造性 |
| 知識の性質 | 客観的、確実、予測可能 | 参加的、文脈依存、確率的 |
| 変化の理解 | 連続的、予測可能 | 非線形、分岐、相転移、創発 |
第7部:統合と展望:21世紀の科学的世界観
カプラのビジョンの実現と拡張
50年前にカプラが『タオ自然学』で提示したビジョンは、現代科学において驚くべき実現を見せています。しかし、それは単なる検証にとどまらず、当初の予想をはるかに超える豊かな発展を遂げています。
理論的統合の達成
学際的統合:物理学、生物学、化学、情報科学、社会科学の境界が溶解し、「複雑系科学」という統一的な枠組みが確立されました。サンタフェ研究所、New England Complex Systems Institute、各国の複雑系研究センターが、この統合の中心となっています。
数学的基礎の確立:ネットワーク理論、非線形動力学、情報理論、カテゴリー理論などにより、複雑系の振る舞いを記述する数学的言語が整備されました。
計算科学の貢献:エージェントベースモデリング、機械学習、量子コンピューティングなどの計算手法により、複雑系の振る舞いをシミュレートし、予測することが可能になりました。
実践的応用の広がり
カプラの思想は、以下の分野で具体的な技術革新と社会変革をもたらしています:
医療革命:
- 精密医療:個人のゲノム、エピゲノム、マイクロバイオーム、環境要因を統合した個別化治療
- ネットワーク薬理学:多標的薬剤の合理的設計
- デジタルツイン:患者の仮想モデルによる治療シミュレーション
- 予防医学:システムバイオマーカーによる疾患の早期予測
持続可能な技術:
- バイオミメティクス:自然の自己組織化原理を模倣した材料・システム設計
- 生物由来材料:自己修復材料、生分解性プラスチック、生体適合性材料
- エネルギーハーベスティング:量子ドット太陽電池、人工光合成システム
- スマートグリッド:分散型エネルギーシステムの自己組織化制御
人工知能の新パラダイム:
- ニューロモルフィックコンピューティング:脳の構造を模倣した省エネルギー計算
- 群知能:アリコロニー最適化、粒子群最適化などの分散型問題解決
- 深層学習の理論的理解:情報幾何学による学習ダイナミクスの解明
- 人工生命:自己複製、進化、適応を示す人工システム
未解決の課題と新たな地平
カプラのビジョンが大きく実現された今、新たな課題と可能性が見えてきています:
意識のハードプロブレム
物理的プロセスからどのようにして主観的体験(クオリア)が生じるのかという「意識のハードプロブレム」は、依然として最大の謎です:
統合情報理論(IIT):ジュリオ・トノーニのIIT 3.0は、意識を統合情報量Φで定量化しようとしていますが、実験的検証は困難です。
オーケストレーテッド客観的還元(Orch-OR):ロジャー・ペンローズとスチュアート・ハメロフの理論は、微小管における量子重力効果が意識を生むと提案していますが、議論が続いています。
予測処理理論:脳が予測マシンであるという理論は、意識の機能的側面を説明しますが、現象的側面は未解明です。
生命の起源
生命がどのようにして無生物から生じたかは、依然として大きな謎です:
RNAワールド仮説:自己複製するRNA分子が最初の生命であったとする説が有力ですが、RNAの非生物的合成は困難です。
代謝優先説:自己触媒的な化学反応ネットワークが先に生じたとする説も提案されています。
パンスペルミア説:生命が宇宙から来たとする説も、起源の問題を先送りするだけです。
社会システムの予測と制御
人間社会の複雑性は、自然システムを超える難しさを持っています:
社会物理学:人間行動の統計的法則性は発見されていますが、個人の自由意志との関係は不明です。
文化進化論:ミームの概念による文化進化の理解は進んでいますが、予測は困難です。
グローバルガバナンス:地球規模の問題に対する効果的なガバナンスメカニズムの設計は喫緊の課題です。
新しい統合への道
21世紀の科学は、カプラが示した方向性をさらに推し進め、より深い統合を目指しています:
量子-古典境界の理解
デコヒーレンス理論:環境との相互作用により量子的重ね合わせが古典的状態に収縮するメカニズムが解明されつつあります。
量子ダーウィニズム:ヴォイチェフ・ジュレックの理論は、古典的現実が量子状態の「自然選択」により創発することを示唆しています。
マクロ量子現象:超伝導、超流動、ボース・アインシュタイン凝縮など、巨視的スケールでの量子現象の理解が進んでいます。
情報と物理の統合
It from Bit:ジョン・ホイーラーの「すべては情報から」という思想は、情報を物理的実在の基礎と見なします。
ホログラフィック原理:宇宙の情報が境界面に符号化されているという理論は、時空の創発的性質を示唆します。
量子情報理論:量子もつれ、量子テレポーテーション、量子暗号などの発展により、情報の量子的性質が解明されています。
生命と非生命の連続性
アストロバイオロジー:地球外生命の探索は、生命の普遍的原理の理解につながります。
合成生命:クレイグ・ベンターらによる人工ゲノムを持つ細胞の作成は、生命の定義を再考させています。
プロトセル研究:脂質小胞と自己複製分子の組み合わせによる原始細胞の構築が進んでいます。
結論:繋がりを生きる、創造的な宇宙に参加する
本稿では、フリッチョフ・カプラの知的探求の軌跡を、イリヤ・プリゴジンの科学的発見と、その後の現代科学の驚異的な発展を織り込みながら辿りました。それは、『タオ自然学』における量子世界の逆説的な統一性から、『生命の網』における自己組織化する生命の認知ネットワークを経て、21世紀の複雑系科学、ネットワーク医学、量子生物学、身体化認知科学へと至る、壮大な思索と実証の旅でした。
カプラの究極的な貢献は、深い相互接続性という世界観が、単なる神秘的な直観や哲学的な嗜好ではなく、現代にとって科学的に首尾一貫し、かつ必要不可欠な視点であることを示した点にあります。プリゴジンが「生命はなぜ存在しうるのか」を物理法則の言葉で語ることを可能にし、マトゥラーナとヴァレラが「生命とは何か」をその組織パターンの言葉で定義し、そしてカプラはこれらの強力な科学的洞察を統合し、私たちがいかに生きるべきかという倫理的・実践的なパラダイムへと昇華させたのです。
さらに重要なことは、1990年代以降の科学の発展が、カプラのビジョンを単に検証するだけでなく、それを大きく拡張し、具体的な技術革新と社会変革につなげたことです。バラバシのネットワーク科学は、「すべてがつながっている」という洞察に数学的精密さを与えました。システム生物学は、生命の統合的理解を分子レベルで実現しました。量子生物学は、量子力学と生命の深い関係を実証しました。そして、これらすべての発展が、医療、エネルギー、農業、教育、ガバナンスなどの分野で、実践的な解決策を生み出しています。
このパラダイムシフトを受け入れることは、単なる知的な営みではありません。それは、私たちが生命の網の中に深く埋め込まれた存在であるという認識を持って生きること、そして宇宙の絶え間ないダンスの中で、責任と畏敬の念、そして参加意識を育むことへの呼びかけです。
気候変動、パンデミック、生物多様性の喪失、社会的不平等といった21世紀の危機は、すべて相互に関連したシステミックな問題です。これらの解決には、カプラが示したような統合的思考と、それに基づく協調的な行動が不可欠です。私たちは、競争と支配のパラダイムから、協力と共生のパラダイムへと移行する必要があります。
最後に、カプラの思想が示す最も深遠な洞察は、宇宙が機械的で死んだものではなく、創造的で生きたプロセスであるということです。私たちはこの創造的プロセスの観察者ではなく、参加者なのです。量子物理学が示すように、観測行為自体が現実を共創造します。生命のオートポイエーシスが示すように、私たちは自らを創造し続ける存在です。そして、ガイア理論が示すように、私たちは地球という巨大な生命システムの一部として、その運命を共に紡いでいるのです。
これこそが、カプラが提唱する、合理的な分析と直観的な叡智の究極的な統合なのです。科学が神秘主義と出会い、西洋が東洋と対話し、人間が自然と和解する。この統合的ビジョンこそが、持続可能で公正で美しい未来への道を照らす光となるでしょう。
私たちは今、歴史的な転換点に立っています。古いパラダイムは崩壊しつつあり、新しいパラダイムが生まれようとしています。カプラとプリゴジン、そして無数の科学者たちが示した道は、単なる理論ではなく、実践への招待です。それは、生命の網の中で意識的に生き、宇宙の創造的なダンスに参加し、すべての生命と共に進化していくことへの招待なのです。
主要参考文献
カプラの主要著作
- Capra, F. (1975). The Tao of Physics. Shambhala Publications.
- Capra, F. (1996). The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems. Anchor Books.
- Capra, F. & Luisi, P.L. (2014). The Systems View of Life: A Unifying Vision. Cambridge University Press.
プリゴジンと散逸構造
- Prigogine, I. & Stengers, I. (1984). Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. Bantam Books.
- Prigogine, I. (1980). From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences. W.H. Freeman.
- Prigogine, I. (1997). The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature. Free Press.
オートポイエーシスと認知
- Maturana, H.R. & Varela, F.J. (1980). Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. D. Reidel.
- Varela, F.J., Thompson, E. & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press.
- Thompson, E. (2007). Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Harvard University Press.
複雑系科学
- Kauffman, S. (1995). At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity. Oxford University Press.
- Holland, J.H. (1995). Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity. Perseus Books.
- Bak, P. (1996). How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality. Copernicus.
ネットワーク科学
- Barabási, A.-L. & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. Science, 286(5439), 509-512.
- Barabási, A.-L. (2016). Network Science. Cambridge University Press.
- Watts, D.J. & Strogatz, S.H. (1998). Collective dynamics of ‘small-world’ networks. Nature, 393(6684), 440-442.
システム生物学
- Kitano, H. (2002). Systems biology: A brief overview. Science, 295(5560), 1662-1664.
- Alon, U. (2007). Network motifs: Theory and experimental approaches. Nature Reviews Genetics, 8(6), 450-461.
- Barabási, A.-L., Gulbahce, N. & Loscalzo, J. (2011). Network medicine: A network-based approach to human disease. Nature Reviews Genetics, 12(1), 56-68.
量子生物学
- Engel, G.S. et al. (2007). Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. Nature, 446(7137), 782-786.
- Lambert, N. et al. (2013). Quantum biology. Nature Physics, 9(1), 10-18.
- Hore, P.J. & Mouritsen, H. (2016). The radical-pair mechanism of magnetoreception. Annual Review of Biophysics, 45, 299-344.
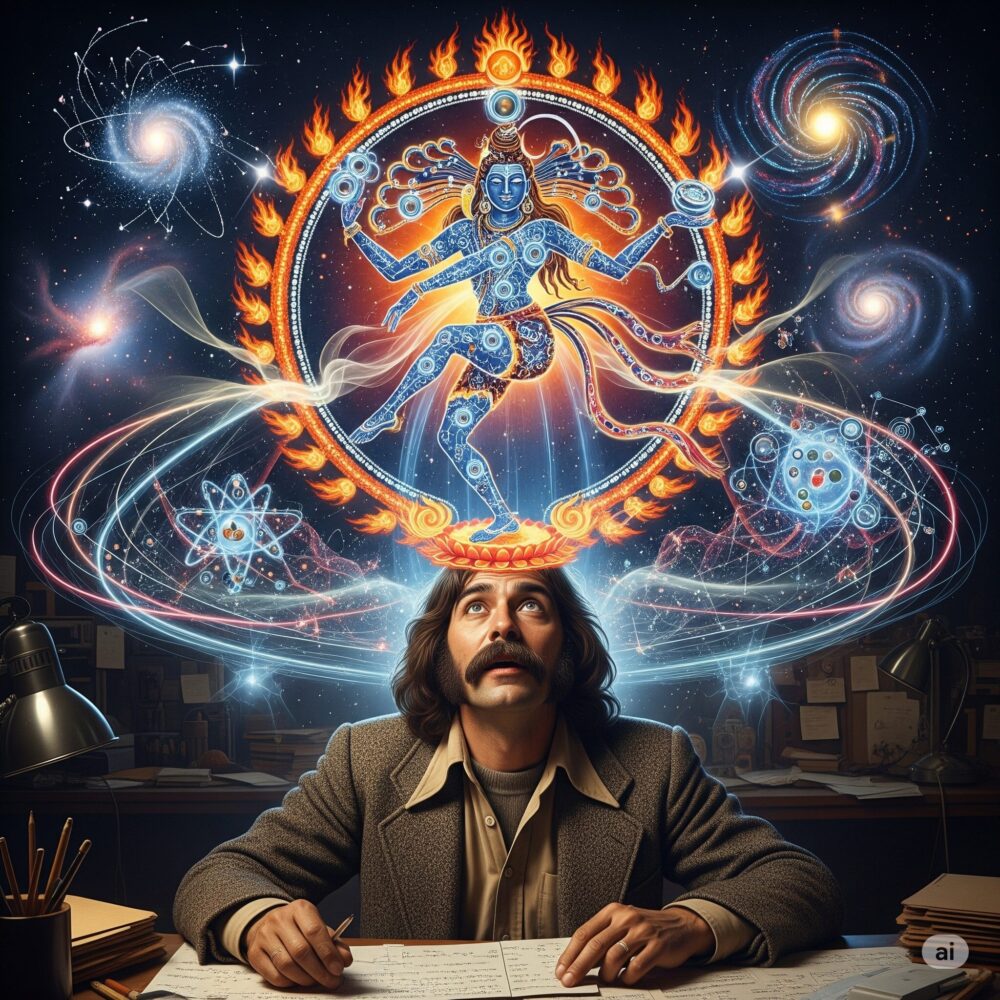
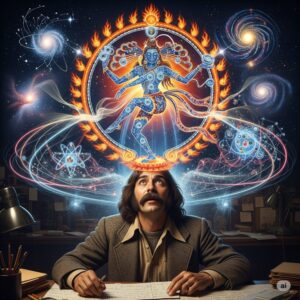
コメント