大切な方を亡くされた悲しみの中、「相続手続きって、一体何から始めればいいの?」「期限があるらしいけど、流れが全くわからない…」そんな深い不安を抱えていませんか。
相続手続きは確かに複雑で、法的な期限も多数存在します。しかし、正しい「流れ」と具体的な「やることリスト」さえあれば、一つひとつ着実に進めることができるのです。
この記事は、相続が初めてで何から手をつけていいか分からない方のために、専門家が相続発生直後から手続き完了までの全貌を、具体的な「やることリスト」を交えて時系列で徹底解説する完全ガイドです。
読み終える頃には、漠然とした不安が「いつまでに、何をすべきか」という明確な行動計画に変わり、自信を持って相続手続きの第一歩を踏み出せるようになっているはずです。
1. 相続手続きの全体像:期限で区切られた「不安のマイルストーン」を理解する
相続手続きは、法的な期限によって明確に区切られています。これらの期限は単なるスケジュールではなく、相続人にとって心理的なプレッシャーを伴う「不安のマイルストーン」として認識されることが多いのです。
相続手続きの5つの重要な期限
相続手続きには、以下の5つの重要な期限があります:
1. 7日以内:死亡届と火葬許可の手続き
2. 14日以内:各種行政手続きと届出
3. 3ヶ月以内:相続の基本方針決定
4. 4ヶ月以内:故人の所得税申告(準確定申告)
5. 10ヶ月以内:相続税の申告と納税
1. 7日以内:死亡届と火葬許可の手続き
大切な方を亡くされた直後の混乱期。葬儀の準備と並行して行う必要がある緊急性の高い行政手続きです。
2. 14日以内:各種行政手続きと届出
年金の受給停止、健康保険証の返却など、故人に関連する各種制度からの離脱手続きを行う期間です。
3. 3ヶ月以内:相続の基本方針決定
相続人の確定、財産調査、そして最も重要な「相続放棄」の判断期限。この期間の調査と決断が、その後の相続手続き全体の方向性を決定づけます。
4. 4ヶ月以内:故人の所得税申告(準確定申告)
多くの人が見落としがちな手続きですが、故人が事業主や不動産所得者だった場合には必須の手続きです。万が一忘れてしまった場合にどのような不都合が生じるかについては、以下の記事を参照してください。
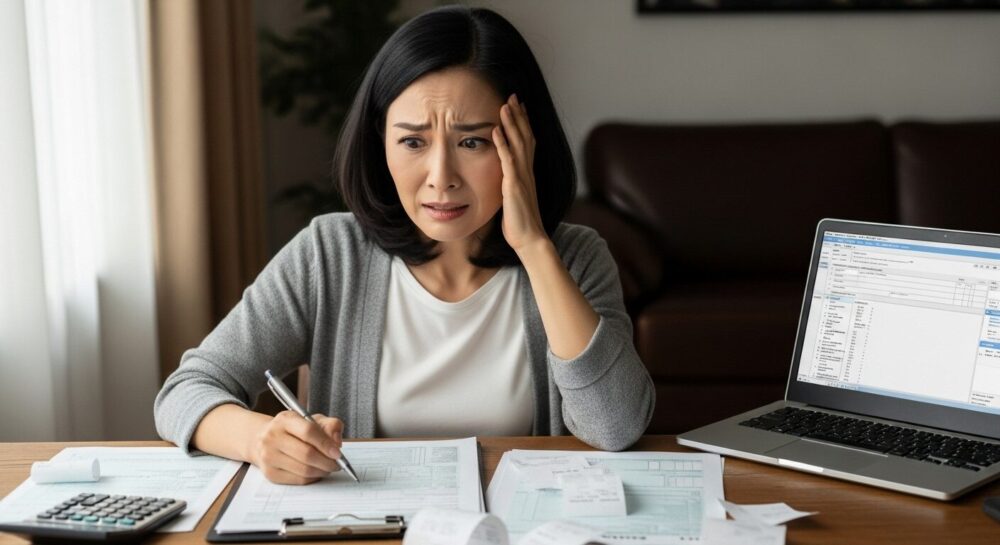
5. 10ヶ月以内:相続税の申告と納税
相続手続きの最終段階。遺産分割協議の完了、相続税の計算と申告、納税まで、すべてをこの期限内に完了させる必要があります。
心理的変遷を理解した手続きの進め方
これらの期限は、相続人の心理的な変遷とも密接に関連しています。
最初の2週間(混乱期)は、悲しみと煩雑な行政手続きが混在する最も困難な時期です。この時期は、必要最小限の手続きに集中し、無理をしないことが重要です。
3ヶ月目(戦略的判断期)は、相続放棄という最初の重大な戦略的判断を迫られる時期です。感情的な判断ではなく、客観的な財産調査に基づいた冷静な判断が求められます。
10ヶ月目(最終決着期)は、相続税申告という最終的かつ重大な期限を迎える時期です。この時点で、すべての相続人間の合意が形成され、具体的な分割内容が確定している必要があります。
このような心理的変遷を理解し、各段階で適切なサポートを受けながら進めることが、円満な相続手続きの鍵となります。
2. 相続発生後14日以内:悲しみの中でも必要な緊急手続き
大切な方を亡くされた直後は、深い悲しみの中にあっても、法的に定められた期限内に完了させなければならない重要な手続きがいくつか存在します。これらは葬儀の準備と並行して進める必要があるため、家族や親族と協力しながら、一つずつ着実に完了させることが重要です。
7日以内:死亡に関する最重要手続き
死亡診断書の取得と死亡届の提出
相続手続きの出発点となるのが、医師から発行される「死亡診断書」または「死体検案書」の取得です[1]。この書類は、死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場へ「死亡届」と共に提出する必要があります。
死亡届の提出は、通常、葬儀社が代行してくれることが多いのですが、家族が直接行う場合は、以下の点に注意が必要です:
- 届出人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、法律で定められた者に限られます
- 死亡診断書は原本が必要ですが、相続手続きでも使用するため、提出前に必ず複数部コピーを取っておきましょう
- 24時間受付の役所もありますが、時間外の場合は翌開庁日に正式な受理となることがあります
火葬・埋葬許可証の取得
死亡届を提出する際に、同時に「火葬許可申請書」も提出し、「火葬許可証」の交付を受けます[2]。この許可証がなければ火葬を行うことはできません。火葬後は、火葬場で「埋葬許可証」に変更されるため、将来の墓地への納骨時まで大切に保管する必要があります。
14日以内:各種行政手続きと金融機関への連絡
年金の受給停止手続き
故人が年金を受給していた場合、速やかに受給停止の手続きを行う必要があります。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に年金事務所へ「受給権者死亡届」を提出します[3]。
この手続きを怠ると、年金が過払いとなり、後日返還手続きが必要になります。特に年金が銀行口座に自動振込されている場合、口座凍結前に振り込まれた年金は、相続人が返還する義務を負うことになるため、注意が必要です。
健康保険・介護保険の資格喪失手続き
国民健康保険や介護保険の資格喪失届を14日以内に市区町村役場へ提出し、保険証を返却します[1]。会社員だった場合は、勤務先の人事部門が健康保険の手続きを行ってくれることが一般的です。
世帯主変更届
故人が世帯主で、世帯員が2人以上残る場合は、14日以内に市区町村役場へ世帯主の変更届を提出する必要があります[1]。新しい世帯主は、残された世帯員の中から選択します。
金融機関への死亡連絡
故人名義の預貯金口座がある金融機関へ、速やかに死亡の事実を連絡します。これにより口座が凍結され、相続手続きが完了するまで入出金が停止されます[2]。
この口座凍結は、一部の相続人による無断の引き出しを防ぐ重要な措置ですが、同時に公共料金の引き落としも停止されるため、ライフラインの継続に支障をきたす可能性があります。そのため、以下の対応も並行して行う必要があります。
公共料金等の名義変更・解約
電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの契約者名義を変更または解約します。特に故人の口座から引き落とされている場合、口座凍結によりライフラインが停止する可能性があるため、早急な対応が求められます[2]。
実家を相続する予定がある場合は名義変更を、空き家になる場合は解約を選択します。ただし、完全に解約してしまうと、後日再契約する際に工事費用がかかる場合があるため、当面の維持費用と比較検討することをお勧めします。
この期間の心構えとサポート体制
この14日間は、悲しみの中で多くの手続きを並行して進める必要がある、最も困難な期間です。一人ですべてを抱え込まず、家族や親族、そして葬儀社などの専門業者のサポートを積極的に活用することが重要です。
また、この時期に慌てて重要な決断を下す必要はありません。緊急性の高い行政手続きに集中し、相続に関する重要な判断は、心の整理がついてから冷静に行うことをお勧めします。
3. 相続発生後3ヶ月以内:人生を左右する重要な意思決定期間
この3ヶ月間は、相続手続き全体の方向性を決定づける最も重要な期間です。財産の全体像を把握し、法的に定められた期限内に、場合によっては人生を左右する重大な決断を下す必要があります。感情的な判断ではなく、客観的な事実に基づいた冷静な判断が求められる時期でもあります。
ステップ1:遺言書の有無の確認
相続手続きの第一歩は、故人が遺言書を遺していないかを徹底的に調査することです。遺言書の存在により、その後の手続きが大きく変わるためです。
公正証書遺言の確認
公正証書遺言は、全国の公証役場で作成された遺言書です。平成元年以降に作成された公正証書遺言は、全国の公証役場で検索することができます[4]。相続人であることを証明する戸籍謄本と身分証明書を持参すれば、最寄りの公証役場で検索してもらえます。
自筆証書遺言の確認
自筆証書遺言は、故人が自分で書いた遺言書です。まず、自宅の金庫、仏壇、書斎、銀行の貸金庫などを探してみましょう。また、2020年7月10日から開始された法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している可能性もあるため、最寄りの法務局でも確認することをお勧めします[5]。
法務局保管以外の自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。この検認手続きには通常1ヶ月以上を要するため、遺言書を発見した場合は速やかに手続きを開始する必要があります[6]。
ステップ2:相続人の確定
法的に誰が相続人となるのかを正確に確定させることは、その後のすべての手続きの基礎となります。遺産分割協議は、法定相続人全員の参加が絶対条件であり、一人でも欠けていれば、その協議は無効となるためです。
戸籍謄本の収集
相続人の確定には、故人の「出生から死亡まで」の連続したすべての戸籍謄本一式を収集する必要があります[6]。これには、現在の戸籍謄本だけでなく、結婚や転籍によって閉鎖された過去の「除籍謄本」や、法改正前の書式である「改製原戸籍謄本」も含まれます。
戸籍についての詳細な解説は以下の記事を参照してください。

収集作業は、まず故人の死亡時の本籍地(最後の本籍地)の役所で除籍謄本を取得し、そこに記載されている「従前戸籍」の情報を頼りに、一つ前の本籍地へと遡っていく作業を繰り返します。
広域交付制度の活用
2024年3月1日から開始された戸籍の「広域交付制度」により、最寄りの市区町村役場の窓口で、本籍地が異なる複数の戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました。これにより手続きは大幅に簡素化されましたが、請求できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)に限られ、兄弟姉妹の戸籍は請求できないなど、制約も存在します。
想定外の相続人の発見
この戸籍調査を通じて、想定していなかった相続人(例:前妻との間の子、認知された子など)が判明することもあります。このような場合、その相続人も含めて遺産分割協議を行う必要があるため、早期の発見と連絡が重要です。
ステップ3:相続財産の徹底調査
相続財産の調査は、単にプラスの財産を見つける作業ではありません。むしろ、予期せぬ負債を発見し、相続全体のリスクを管理する上で極めて重要なプロセスです。特に、相続放棄の3ヶ月という短い期限を考慮すると、負債の調査は最優先で着手すべきです。
プラス財産の調査
不動産の調査:毎年送付される「固定資産税の納税通知書」が最も確実な手がかりです。もし見つからない場合でも、市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得すれば、その自治体内に故人が所有していた不動産の一覧を確認できます。
預貯金の調査:通帳やキャッシュカードが見つかれば、その金融機関の窓口で「残高証明書」の発行を依頼します。これにより、死亡日時点の正確な残高が確定します[11]。
有価証券の調査:証券会社からの「取引報告書」や「配当金支払通知書」を探します。取引のある証券会社が不明な場合は、「証券保管振替機構(ほふり)」に情報開示請求を行うことで、故人が口座を開設していた証券会社を調べることができます。
マイナス財産(負債)の調査
借入金の調査:消費者金融からの契約書や督促状、預金通帳の定期的な引き落とし履歴などを確認します。心当たりがない場合でも、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に情報開示請求を行うことで、ローンやクレジットカードの契約状況を網羅的に調査することが可能です。
保証債務の調査:故人が他人の借金の保証人になっていた場合、その債務も相続の対象となります。契約書や保証書の控え、金融機関からの通知などを注意深く確認する必要があります。
3ヶ月の期限:相続放棄・限定承認の選択
財産調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」を選択することができます。また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」という方法もあります。
相続放棄の重要性
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があり、この期限は原則として延長できない極めて重要なものです[13]。
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされ、故人の債務を一切承継しません。ただし、相続放棄後は、プラスの財産も一切相続できなくなるため、慎重な判断が必要です。
限定承認という選択肢
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することです[14][15]。つまり、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、それを超える借金については責任を負わないという制度です。
ただし、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があり、一人でも反対者がいれば利用できません。また、手続きが複雑で時間もかかるため、実際に利用されるケースは多くありません。
期間の伸長申立て
財産調査が複雑で3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます[15]。ただし、この申立ては3ヶ月の期限が経過する前に行う必要があり、正当な理由が認められる場合に限り、通常3ヶ月程度の延長が認められます。
この期間の戦略的思考
この3ヶ月間は、感情的な判断ではなく、客観的なデータに基づいた戦略的思考が求められます。特に、農地や事業用資産など、評価が困難な財産が含まれる場合は、専門家のアドバイスを早期に求めることをお勧めします。
また、相続放棄は一度行うと撤回できないため、将来的な財産価値の変動や、他の相続人の動向も考慮した総合的な判断が必要です。迷った場合は、期間の伸長申立てを行い、十分な時間をかけて検討することが賢明です。
4. 相続発生後4ヶ月以内:故人の所得税申告(準確定申告)
多くの人が見落としがちな手続きが、故人の所得税に関する「準確定申告」です。これは、故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わって確定申告を行う手続きです[16]。
準確定申告が必要なケース
準確定申告が必要となるのは、以下のような場合です:
事業所得や不動産所得があった場合:故人が個人事業主として商売を営んでいた場合や、アパート経営などで不動産所得があった場合は、必ず準確定申告が必要です。
給与所得者でも申告が必要な場合:年収が2,000万円を超えていた場合、2ヶ所以上から給与を受けていた場合、副業による所得が20万円を超えていた場合などは、給与所得者であっても準確定申告が必要です[16]。
医療費控除等を受ける場合:故人が多額の医療費を支払っていた場合、準確定申告により医療費控除を受けることで、所得税の還付を受けられる可能性があります。
申告期限と手続きの注意点
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内と定められており、通常の確定申告の期限(翌年3月15日)とは異なるため、特に注意が必要です[1]。
申告書の提出は、故人の住所地を所轄する税務署に行います。相続人が複数いる場合は、連署により申告書を提出するか、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
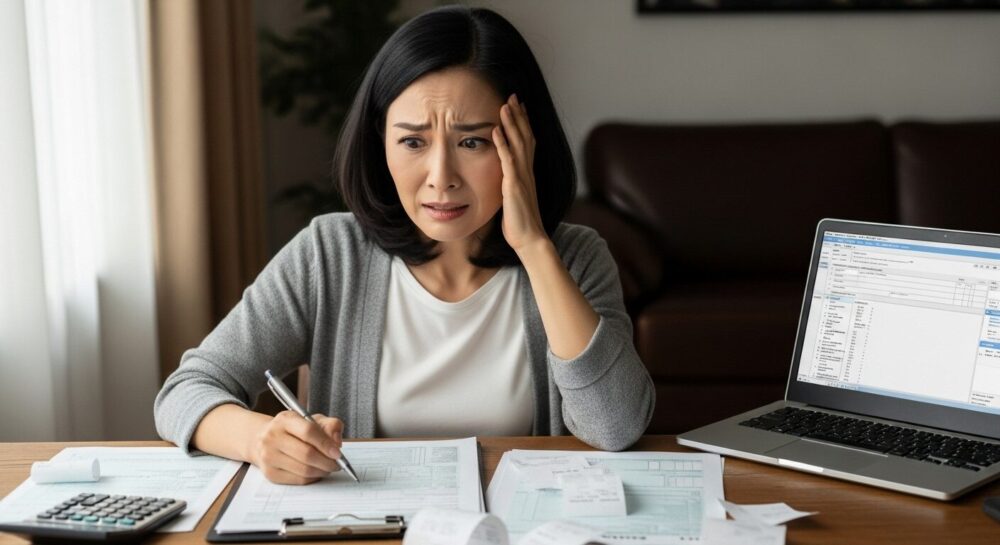
準確定申告のメリット
準確定申告を適切に行うことで、以下のようなメリットがあります:
- 所得税の還付を受けられる可能性がある
- 故人の所得を正確に把握することで、相続税申告の基礎資料となる
- 税務署との関係を良好に保ち、後の相続税申告をスムーズに進められる
5. 相続発生後10ヶ月以内:相続税申告と納税の最終段階
相続手続きの最終段階となるのが、相続税の申告と納税です。この期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内であり、申告書の提出と納税の両方をこの日までに完了させなければなりません。
10ヶ月に向けた準備プロセス
財産の評価
相続財産を適切に評価することは、相続税申告の基礎となります。ここで重要なのは、財産の評価額には複数の基準があるという点です。
不動産の場合、相続人間で公平に分けるための「時価(実勢価格)」と、相続税を計算するための「相続税評価額」は必ずしも一致しません[1]。特に農地や事業用資産では、この差が大きくなる傾向があります。
遺産分割協議の完了
相続税の申告期限までに、相続人全員による遺産分割協議を完了させる必要があります。この協議では、誰がどの財産をどれだけ相続するかを具体的に決定し、「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
遺産分割協議書には、以下の内容を明記する必要があります:
- 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所・本籍
- 各相続人が取得する財産の詳細(不動産は登記簿通りに、預貯金は銀行名・支店名・口座番号まで正確に記載)
- 相続人全員の署名と実印での押印
- 各相続人の印鑑証明書の添付
相続税の計算
相続税の計算は、以下の4つのステップで行われます:
- 課税価格の合計額の算出:全相続財産の相続税評価額を合計し、借入金や葬儀費用を差し引いて「正味の遺産額」を算出します。
- 課税遺産総額の算出:正味の遺産額から「基礎控除額」を差し引きます。基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です[18]。この時点で結果がゼロ以下になれば、相続税はかからず申告も不要です。
- 相続税の総額の算出:課税遺産総額を、一旦、法定相続分で分割したものと仮定して、各相続人の取得金額を算出します。それぞれの金額に税率を適用し、控除額を引いて各人の税額を計算し、それらをすべて合計したものが「相続税の総額」となります[18]。
- 各相続人の納税額の算出:算出した「相続税の総額」を、実際に財産を取得した割合に応じて按分し、各相続人が実際に納める税額を決定します[19]。
遺産分割協議書の作成手続きの詳細については、以下の記事を参照してください。

相続税の軽減制度の活用
- 配偶者税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 生命保険金の非課税枠
相続税には、税負担を軽減するための様々な特例制度があります。これらを適切に活用することで、大幅な節税が可能になる場合があります。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産については、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です[20]。この制度を利用すれば、一次相続の税負担をゼロにすることも可能です。
ただし、この制度には「二次相続」の問題があります。一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、その配偶者が亡くなった際の二次相続では、相続財産が膨らんだ状態で子供たちが相続することになり、結果的に一次・二次相続を合わせたトータルの税負担が増加してしまう可能性があります[21]。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた自宅の敷地(特定居住用宅地等)を一定の要件を満たす親族が相続した場合、その土地の評価額を最大で80%減額できる制度です[22]。
適用要件は、誰がその土地を相続するかによって厳格に定められています:
- 配偶者:無条件で適用可能
- 同居していた親族:相続税の申告期限までその土地を所有し、かつその家に居住し続けることが要件
- 同居していない親族(いわゆる「家なき子」特例):被相続人に配偶者や同居の相続人がいない場合に限り、非常に厳しい要件をすべて満たす必要がある[23]
生命保険金の非課税枠
相続人が受け取る生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています[24]。この制度を活用することで、相続税の負担を軽減しつつ、納税資金を確保することができます。
申告と納税の実務
相続税の申告書は、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。申告書の作成は非常に複雑であり、特例制度の適用要件も厳格であるため、税理士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。
納税は、申告期限と同じ10ヶ月以内に行う必要があります。現金での一括納付が原則ですが、納税額が大きい場合は「延納」や「物納」という制度も利用できます[25]。
期限に遅れると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるため、期限の厳守が極めて重要です[26]。
申告後:財産の名義変更手続きで相続を完結させる
相続税の申告・納税が完了しても、相続手続きはまだ終わりではありません。各財産の法的な所有権を故人から相続人へ移転させる「名義変更」が必要となります。この手続きを怠ると、将来的に二次相続が発生した際に手続きが複雑化したり、財産の処分ができなくなったりする可能性があります。
不動産の相続登記(3年以内の義務)
相続登記の義務化
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務が生じることになりました[27]。期限内に登記しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の手続き
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。必要な書類は以下の通りです:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登記申請書
手続きは司法書士に依頼することが一般的ですが、相続人自身で行うことも可能です。登録免許税として、不動産の固定資産税評価額の0.4%が必要となります[28]。
預貯金・有価証券等の名義変更
金融機関での手続き
故人名義の預貯金口座は、死亡の連絡により凍結されています。この凍結を解除し、相続人名義に変更または解約・払い戻しを行うには、各金融機関で所定の手続きが必要です[29]。
一般的に必要となる書類は以下の通りです:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 通帳・キャッシュカード
- 各金融機関所定の相続手続依頼書
証券会社での手続き
株式や投資信託などの有価証券についても、同様の手続きが必要です。証券会社によって手続きの詳細は異なりますが、基本的な必要書類は預貯金の場合と同様です[30]。
農地特有の手続き
農業委員会への届出
農地を相続した場合、不動産としての相続登記とは別に、所在地の農業委員会へ相続した旨を届け出る必要があります。この届出は、権利を取得したことを知ってから10ヶ月以内に行うことが定められており、怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります[31]。
この届出は農地特有の手続きであり、見落とされやすいため特に注意が必要です。届出書は各農業委員会の窓口やホームページで入手できます。
相続手続きマスターチェックリスト:あなたの進捗を確認しよう
以下のチェックリストを活用して、相続手続きの進捗を管理し、次に行うべきことを明確にしましょう。このリストを印刷し、手元に置いて一つずつチェックしていくことをお勧めします。
【緊急度:最高】相続発生後すぐ~14日以内
7日以内:死亡診断書の取得
7日以内:死亡届の提出
7日以内:火葬許可申請書の提出
10日以内:厚生年金受給停止手続き
14日以内:国民年金受給停止手続き
14日以内:健康保険・介護保険証の返却
14日以内:世帯主変更届(該当する場合)
速やかに:金融機関への死亡連絡(口座凍結)
速やかに:公共料金等の名義変更・解約
【緊急度:高】相続発生後3ヶ月以内
遺言書の有無確認(公証役場・法務局・自宅等)
自筆証書遺言の検認申立て(発見した場合)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本収集
相続人全員の現在戸籍謄本取得
相続関係説明図の作成
相続財産調査(プラス財産)
不動産(固定資産税納税通知書・名寄帳)
預貯金(残高証明書取得)
有価証券(証券会社への照会)
その他の財産(貴金属・美術品等)
相続債務調査(マイナス財産)
借入金の確認
信用情報機関への照会
保証債務の確認
重要:相続放棄・限定承認の判断と申述(必要な場合)
相続の承認又は放棄の期間伸長申立て(必要な場合)
【緊急度:中】相続発生後4ヶ月以内
準確定申告の要否判定
準確定申告書の作成・提出(必要な場合)
準確定申告に係る所得税の納付(必要な場合)
【緊急度:中】相続発生後10ヶ月以内
相続財産の評価額算定
遺産分割協議の実施
遺産分割協議書の作成
相続税の概算計算
相続税申告書の作成
相続税の申告・納税
各種特例制度の適用検討
配偶者の税額軽減
小規模宅地等の特例
農地の納税猶予制度(該当する場合)
【緊急度:低】相続発生後3年以内
義務:不動産の相続登記申請
預貯金の名義変更・解約手続き
有価証券の名義変更手続き
農地の場合:農業委員会への届出(10ヶ月以内)
その他財産の名義変更手続き
【継続的】その他の重要事項
専門家(行政書士・司法書士・税理士等)への相談
相続人間のコミュニケーション維持
重要書類の整理・保管
二次相続対策の検討
まとめ:不安から確信へ、一歩ずつ確実に
相続手続きは確かに複雑で、多くの期限と手続きが存在します。しかし、本記事で解説した時系列に沿って一つずつ着実に進めていけば、必ず完了させることができます。
最も重要なのは、一人ですべてを抱え込まないことです。各段階で適切な専門家のサポートを受けながら、家族や親族と協力して進めることが、円満な相続手続きの鍵となります。
特に、3ヶ月以内の相続放棄の判断、10ヶ月以内の相続税申告、3年以内の相続登記など、法的な期限が定められている手続きについては、早めに専門家に相談することをお勧めします。
あなたの相続手続きが、故人への最後の贈り物として、そして残された家族の新たな出発点として、円満に完了することを心より願っています。
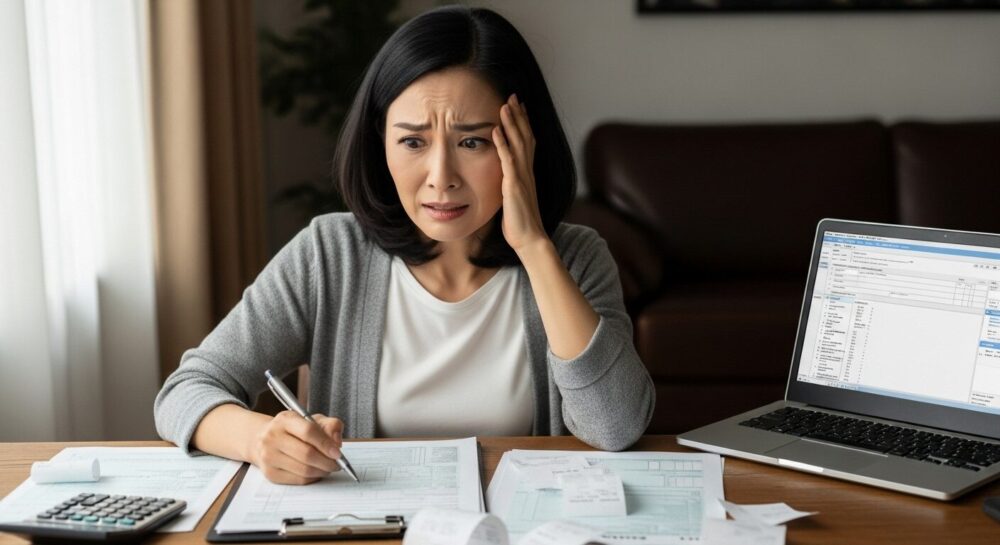
参考文献
[1] 相続手続きの流れ|手順・期限・必要書類をわかりやすく解説. https://souzoku-pro.info/columns/tetsuzuki/34/ [2] 相続の手続きを時系列で紹介!「期限別のスケジュール」で分かりやすく解説. https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku/113-tetsuduki-kigenbetsu-schedule/ [3] 相続手続きの期限 | 相続のいろは – 三菱UFJ信託銀行. https://www.tr.mufg.jp/shisan/souzoku_iroha/tetsuduki_nagare/schedule.html [4] 公正証書遺言の検索制度について – 日本公証人連合会 [5] 自筆証書遺言書保管制度 – 法務省. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html [6] 遺産相続手続きの流れは?期限・必要書類・代行依頼先など基本を解説. https://www.hasegawa.jp/blogs/shukatsu/inheritance-procedure [11] 相続手続きで必要な『戸籍一式』『遺産分割協議書』『印鑑登録証明書』. https://chester-tax.com/encyclopedia/8166.html [12] 信用情報機関への情報開示請求について [13] 相続放棄の期間は3ヶ月!期限を過ぎた時の対処法や期間伸長の申立て. https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/renunciation-of-the-inheritance-2 [14] 相続の承認又は放棄の期間の伸長 – 裁判所. https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html [15] 相続放棄の期間は3ヶ月!いつから数える?手続きと期限切れの対処法. https://chester-tax.com/encyclopedia/9556.html [16] 準確定申告について – 国税庁 [17] 遺産分割協議を円満に進めるための準備と当日の注意点 [18] No.4155 相続税の税率 – 国税庁. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm [19] 相続税はいくらまで無税か徹底解説【2024年】計算方法と判断基準. https://www.taxlawyer328.jp/inheritance-columns/souzoku/p5460/ [20] 配偶者の税額軽減について – 国税庁 [21] 二次相続で不利にならない配偶者控除はシミュレーションが大事. https://ohori-kaikei.com/sozoku/nijisouzoku-haiguusyakoujyo/ [22] No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)- 国税庁. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm [23] 小規模宅地等の特例とは? 適用要件から計算例 – 相続会議. https://souzoku.asahi.com/article/13646590 [24] 生命保険金の相続税非課税枠について – 国税庁 [25] 相続税の延納・物納制度について – 国税庁 [26] 相続税の無申告加算税・延滞税について [27] 相続登記の申請義務化に関するQ&A – 法務省. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html [28] 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)- 法務局. https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html [29] 相続手続きで戸籍と印鑑証明書が必要な理由と集め方. https://www.i-sozoku.com/navi/koseki-inkan/ [30] 有価証券の相続手続きについて [31] 農地相続ポータル – 農林水産省. https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な相続手続きについては、必ず専門家にご相談ください。


コメント